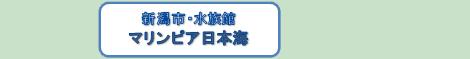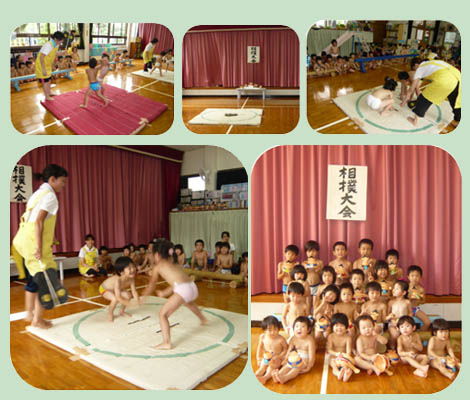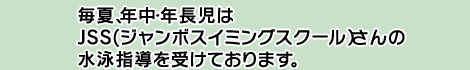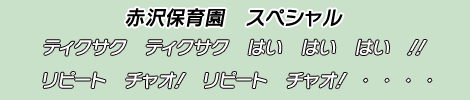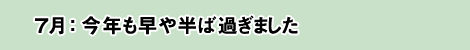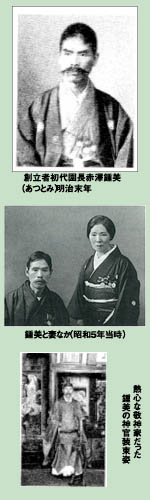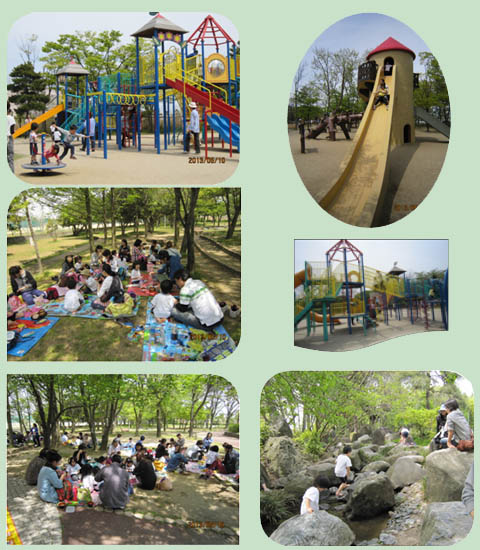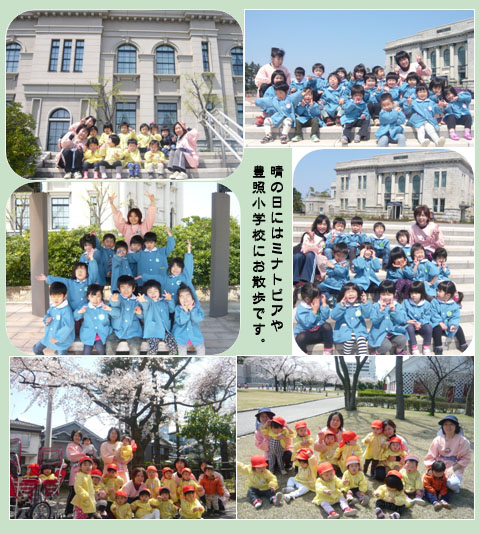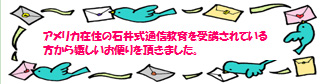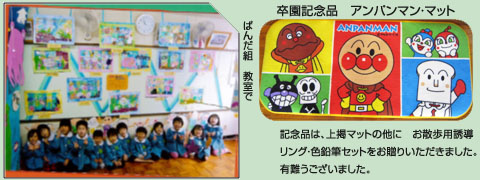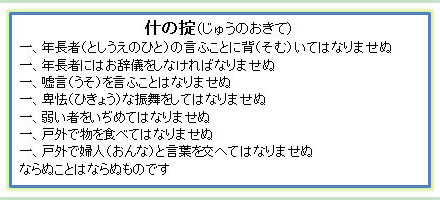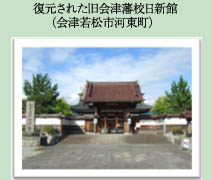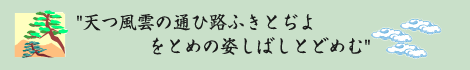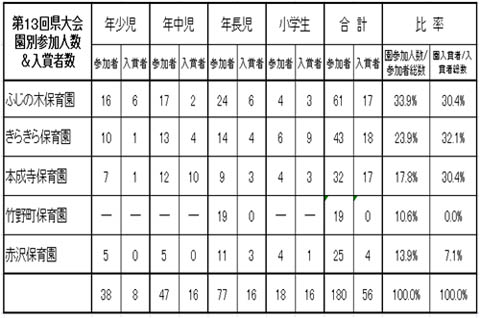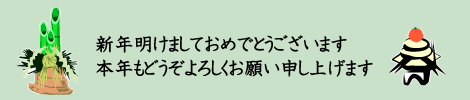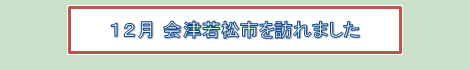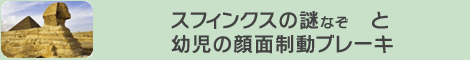
上記の写真はエジプトの首都カイロ市郊外のスフィンクス像とピラミッドですが、遥か離れた私ども日本人にとってもおなじみです。
人間の女性の顔と乳房を持ち胴体はライオンのスフィンクスは、ご当地の神話によるとその前を通る旅人に謎(なぞ)を問いかけてそれが解けなかった旅人を次々に食い殺したとのこと。
その謎とは「朝は四本足、昼になると二本足、夜は三本足となるものは何か?」です。皆さん分りますか。答えられなければ食い殺されたのです。
その答えは「人間」です。人は初めは手をつかってはいはいしながら動きます。やがて二本足で立ちあがり、晩年は杖の助けを借り三本足となり、一生を終るということです。
大略生後五カ月前後に寝返りが出来るようになりやがてはいはいの時期を経て一歳前後でよちよち歩きができるようなる。畳敷きの場合、フトンの上から幼児ははいはいして広い床の上を動き回る事が出来るが最近はフローリング床が多くなり、しかもベビーベッドの場合じかに広い床に行けなくなった。そのためもあってか近頃の子どもは、はいはいの時期がほとんどないまま歩き始める。
しかし実はその はいはいの時期に胸や腕の筋肉が発達し腕で上体を支える訓練になるのです。その結果上体バランスをとるためすぐに腕が出るようになる。 が、最近の幼児は転んだとき手が出なくて顔面をじかにぶつけて顔を大きく損傷するケースが増えているとのこと。はいはいの時期はそれなりの大切な意味あるコースなのです。それを飛び越えていきなり歩いたと言って一概に喜ぶことは早計、スフィンクスの謎のように人の一生にはいはいは当然必要なコースであることを思い出して下さい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
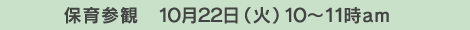

まずいつもの「朝の歌」を元気な声で歌う。次に漢字絵本「月へ行った兎」を漢字カード「月!、兎!、花!」を子ども達の元気な読み声と共に読み聞かせ。続いて準備本番の『切り紙あそび』。保護者の方も一緒に切ったり折ったりして作り上げた「冠」かぶって記念撮影。すてきな時間でした。参観の方々のご協力有難うございました。

紙しばいや写真カードを使って、食べ物には「赤の仲間(骨や筋肉を作るもの)」、「黄色の仲間(エネルギーになるもの)」、「緑の仲間(身体の調子を整えるもの)」がある事を学びました。これから寒くなりますが、バランスよく食べて、病気にならずに元気に過ごして欲しいと思います。

マルコ先生の『英語あそび』の時間をみていただきました。4月からスタートですがとても上手になりました。マルコ先生やお友達との英語での挨拶などの掛け合いなどでしたが誇らしげな14人でした。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
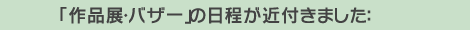
今年恒例の年中行事「作品展&バザー」は来る11月9日(土)開催を予定しております。今、子ども達は作品展の準備に大忙し。どんな風に仕上がりますかお楽しみ。
今年のバザー食品関係業者さんに変更があります。
お団子が餅菓子老舗の「田中屋」さんに、巻きずしが西区内野町の「瀧ずし」さん、そして新しく本町12出身の若手パン屋さん西区小針に出店している「ドリームハウス」さんが加わりました。これまたお楽しみ。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー