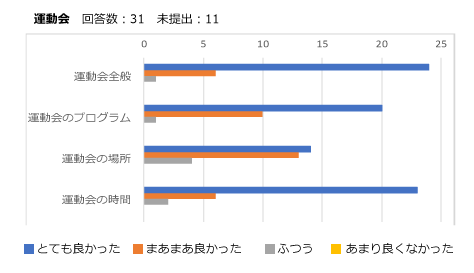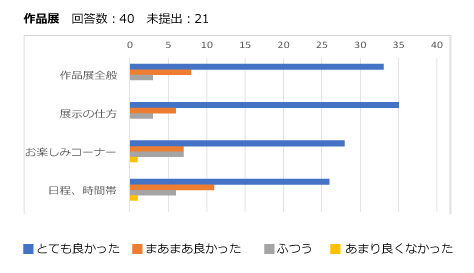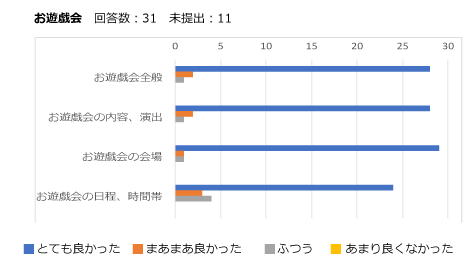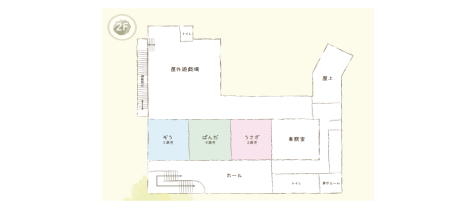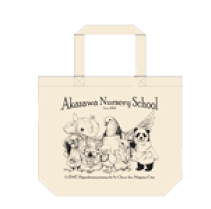どの局のどういった番組だったか覚えていないのですが、先日たまたま目にしたテレビ番組につい見入ってしまい、とても感動してしまったことがあります。
始めは『最近こういう類の(ロボットが接客する最先端技術を体験できる)サービスが増えてきたな』という印象でロボットが働いているカフェの映像を何気なくながめていたのですが、その店で働くロボットたちは、実は遠く離れた場所から、何らかの理由で働くことも外出することも困難な人たちが操っているというのです。その遠隔で働いている人たちの中には難病で眼球しか動かせない重度の障害を持つ人もいて、視線による入力といった最先端のテクノロジーでロボットを操縦し、接客もこなしているのだそうです。そして遠隔で働く彼らには当然のことながら働いた分のお給料が支払われているのです。
このカフェを運営する人物は過去に引きこもりを経験し、その時の体験がこのロボットカフェをオープンさせる大きな原動力になったのだそうです。様々な状況下で外出や働くことができない人々とその家族に大きな希望の光と社会とのつながりを与えた彼の功績は偉大で感動するとともに、このような発想が生まれにくい利益追従型の世の中や働き方も、このコロナ禍を機に何か大きく変革しなければいけない時期に差し掛かっているのではないか、と番組を観終わった後もしばし深く考えさせられたのでした。
私の知人で動物の保護活動を個人ボランティアで精力的に行っている人がいます。彼女の献身的かつ情熱的な活動は、時に「そこまでする?家族や彼女自身は大丈夫なの?」とハラハラさせられることもあるのですが、そんな彼女の熱心な活動はSNSを通じ多くの人の支持と共感を得ているのです。そんな彼女も過去の多感な時期に引きこもった経験があり、その時に唯一彼女の心を支えてくれた動物たちに今は恩返しをしているのだそうです。
両者ともに望んで引きこもったわけでもなく、その間には本人も周囲も想像を超えるほど悩み苦しんだに違いないはずです。でもその長く苦しい時期があったからこそ、現在の彼らがいて、それはまさに「人生において無駄な時間や出来事など何一つない」ことを体現しているのです。
今現在、たとえそれが失敗や無駄、ネガティブに見える物事の渦中にいたとしても、それは将来の大きな飛躍への助走であり必要な充電時間なのだと思います。