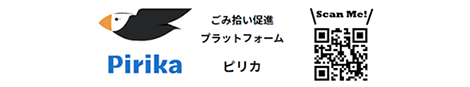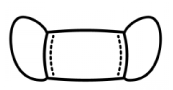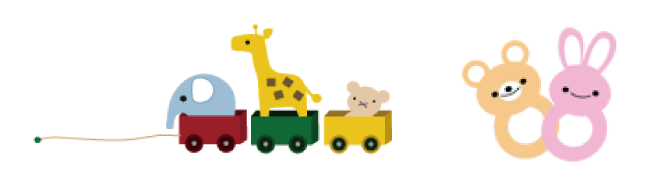先月に引き続き、今月も SDGs にまつわるお話をしようと思います。
さて、SD Gs については多少の理解は深まったけれど、では個人として何ができるのだろう、 何から始めたら良いのだろう、と思っている方もいらっしゃると思います。今日は個人でも気軽に始められそうな SDGs 活動を二つご紹介したいと思います。
最近「ダーニング」という言葉を知りました。ご存じの方もいるかと思いますが、ダーニングとは、穴が開いたり擦り切れてしまった衣服を補修する方法で、古く からヨーロッパを中心に行われてきた技法です。ダーニングには主に二通りのや り方があるようで、一つはその衣服の色と同じ糸で目立たないように補修する 方法と、もう一つは逆に目立つ色をいくつも使い、繕った跡をその衣服の新た な個性として生かす方法です。最近にわかに巷ではやっているのは後者の方 で、装飾ダーニングと呼ばれています。私も見様見真似でやってみましたが、 これがなかなか面白いのです。機会があればワークショップなどに参加して基 礎からダーニングの方法を習ってみたいものです。ダーニングは趣味としての楽 しみも味わえますが、何よりも傷んでしまった衣服に再び命を吹き込み『捨てる』以外の選択肢を与えられるのはすばらしいことではないでしょうか。
これからの季節、海水浴やキャンプに行く機会も増えてくることと思いますが、砂浜やキャンプ場などでポイ捨てされたゴミを見て不快な気分になった経験は 誰でも一度はあるかと思います。けれど不快に思うだけでなかなか『拾う』という行動にまでは及びません。ゴミ拾いはボランティア活動などのきっかけや一緒にやる仲間がいないと、個人ではなかなか『 拾う』勇気が持てないものです。でも「ピリカ」はグループでのイベントはもちろん、個人のごみ拾いもサポートしてくれるアプリで、自分が拾ったごみの情報をピリカのアプリを使って投稿することで、世界中で拾われたごみのカウントに自分の拾ったごみの数が加算される仕組みになっています。ボランティア活動は決して誰かに見てもらい褒められることを前提として行うものでは無いけれど、人知れずひっそりやるのもむなしいものです。ポイ捨てされるごみが無くなってくれることが一番ですが、日常生活の中で「ごみを見つけたら拾って捨てる」習慣が世界中の人々に広がれば、将来の地球は少しずつきれいになっていくことでしょう。