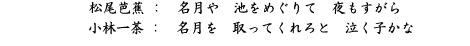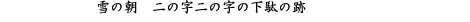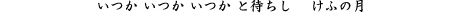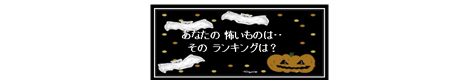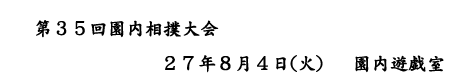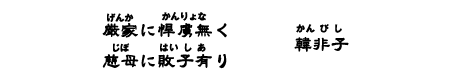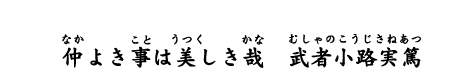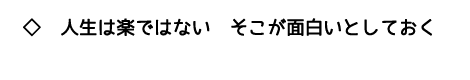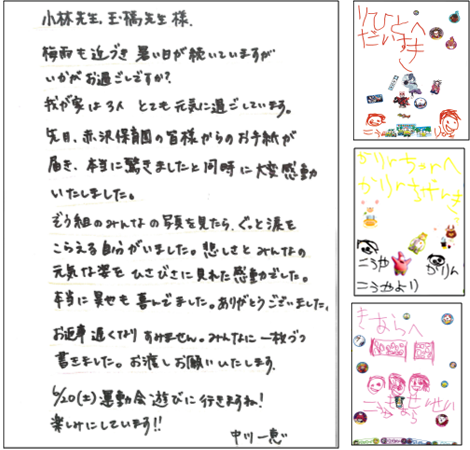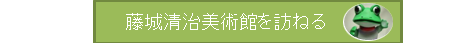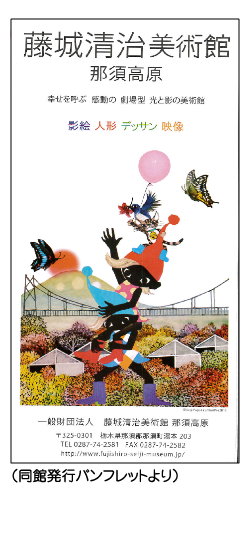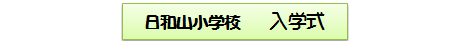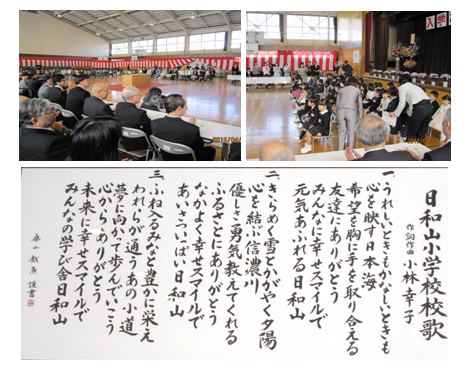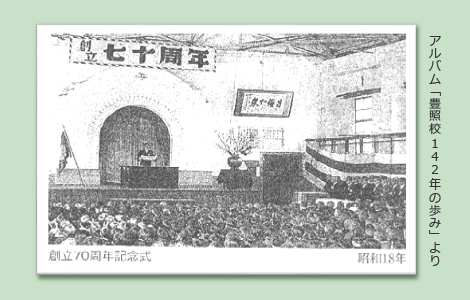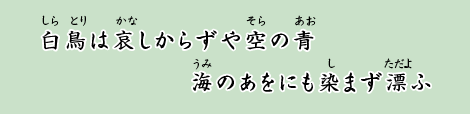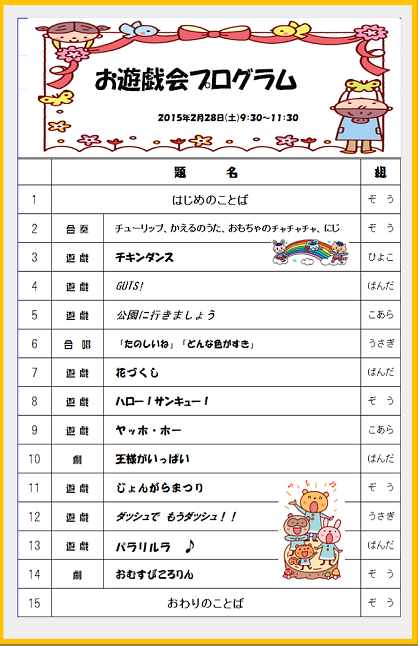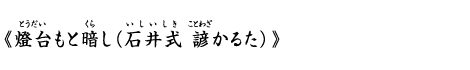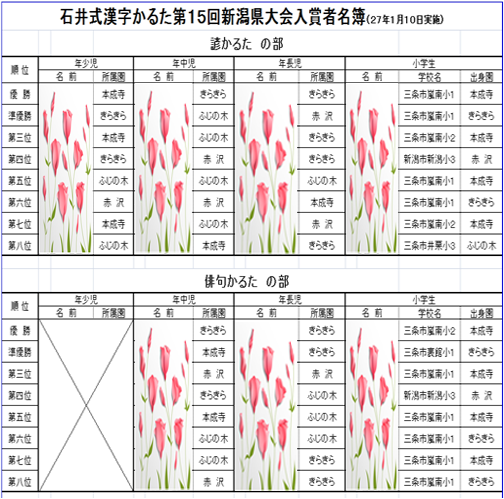平成18年大月書店発行『保育小辞典』の「三歳児神話」の項目には次の様に記述されている。
”「3歳までは母親が子育てに専念しないと乳幼児の発達に悪影響が出る」という考え方。現実とは合致しないという意味で「神話」という言葉が付加されている。母性剥奪理論が理論的根拠とされる。乳幼児を持つ母親が働くこと、保育所に子どもを預けることに対する罪悪感や不安を産み、女性の生き方を制約してきた。理想とされた専業の母親における育児不安の広がり、共働きの急増、3歳児神話に合理的根拠はないとした『平成10年版厚生白書』など、3歳児神話をめぐる議論も転機を迎えている。”

園長の解説だけでは偏りがあってはいけないと考えて辞書を引用したがどうも学者先生の解説は分かりにくい。
要は三歳児神話とは三歳までは親が直接保育することが望ましく義務であり、親が最善の保育者であるとの観点に立っている。その期間は親が直接保育すべきであり、それを施設なり他者に依頼することは子どもの生育将来に取り返しのつかない禍根を生じることになる、との考え方が基本だった。あらゆる点で男性優位の昭和の半ば頃までは両親共働きは子育てには無理があり、男が外で働き女は家事育児に専念従事することが好ましいとの考え方が昭和時代の中頃までは支配的だった。
その後、職場環境の男女同権意識が高まり男女間の賃金格差も基本的に無くなり女性が働きやすい環境になってきた。また結婚早々ローンで家やその他を購入したりでその返済のため共働きが常態の生活構造にもなってきた。
しかし、そのような社会構造の変化の中にあっても子育て真っ最中の親にとって子育ての大部分に親が直接関われないもどかしさとうしろめたさから、このまま保育園に任せておいて子どもの将来に問題を残さないかどうかの懸念は誰しも多かれ少なかれ抱いている。かといって専業家庭主婦として子育てに専念を心掛けても、現今の一般的な家庭の環境は、ほとんどの家庭が核家族化し近隣との交流もすくなくなり、公園などに行っても同年の子どもに出会う事もほとんど無く、むしろ路上生活者や不審者と遭遇して不安な思いをするのが現実である。といっても高層階のマンション住宅の一室に親子だけで閉じこもる生活を繰り返していては、子どもにとって母親以外の他人と接することのない閉じこもり症候群生活突入のための早期訓練をしているようなものだ。
三歳児神話が生成された大正から昭和中期頃と平成の現在とではあまりにも子育て環境や社会構造が大きく変化してきた。それにつれて神話は時代に合わない過去の話のはずだった。ところがところである。

現首相安倍晋三氏が最初の首相の座を健康事情のため一年ほどで辞職。その後健康回復され、第二次安倍内閣が2012年(平成24年)12月に発足、以来現在に至っている。
第二次内閣発足の翌年平成25年4月、首相官邸内記者クラブで安倍首相は「成長戦略スピーチ」を発表した。 首相はその戦略スピーチの中で、外交問題、経済問題等々に続いて「女性が輝く日本」の構築を目指す事を宣言した。
その「女性が輝く日本」の具体策としてまず大企業における管理職・役員に女性を多く登用することを経済団体を通して企業に要請した。とはいえ結婚や出産、育児のために職場を離れる女性が少なくないことも現実だ。そのために保育所を充実して入所希望に全面的に受け入れる待機児童ゼロの体制に持っていく。出産や育児のために離職する事がないよう3年間は子どもを抱っこし放題出来るように企業に3年育休を与えるように助成金などの施策も考えている‥、と記者団に総理は宣言した。公務員は「3年育休」はすでにしっかりとりいれている。
昭和29年生まれの安倍総理、大正14年生まれの父親安倍晋太郎氏に育てられている。問題の多い「三歳児神話」はすっかり総理の脳裏に刷り込まれているようだ。「3年間抱っこし放題」で育てる事が育児法としてどうかはここでは論じません。
神話はあくまでも虚実取り混ぜありが神話であり、真理・真話ではない。 古代中国の学者韓非子(カンピシ)の言「慈母に敗子あり」(優しいばかりの母親は子どもをダメにする)が脳裏に浮かんでくる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


年中行事の大きな楽しみの一つ『芋掘り遠足』、最初の平成3年秋に実施以来、江南区酒屋町を毎年訪問、今回で25回になります。
変わりやすいものの例えが「秋の空」、天候不安定なこの時期ですが、これまで一回も雨による変更なしで続けました。赤沢保育園遠足日は晴と酒屋町の方々は噂されてるそうで‥。
10月9日(金)、今回もこれ以上なしの好天に恵まれました。時期としては遅めでしたのでいものサイズは大き目でしたが、味は上々、栗に負けないホクホク食感です。 皆様のご協力に感謝申し上げます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー